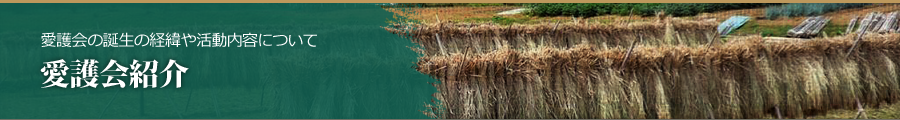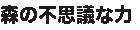雑木林のコナラやクヌギが秋でもないのにあちこちで色付きというか枯葉が目立っていますが、どうしたことでしょうか。 森林資源の利用が減り雑木林に手が入らなくなり久しくなりますが、その間に樹齢を重ね太くなったコナラ、クヌギの大木がナラ枯れ病菌に侵されている姿です。でも雑木林は私たちの身近にあり、 昭和30年ごろまでは燃料用として20年生前後で伐採されていたのでナラ枯れ菌による被害も少なく枯れ木も目立たず、切り株からの芽(萌芽)により林が更新され、長い間便利に利用し続けてきた林でした。
1.萌芽
落葉広葉樹で構成されている雑木林の樹木たちは、伐採されると切り株から新しい芽を出し自分の体を再生させる性質を持っています。この新しく出る芽を萌芽といいます。この萌芽のもとになるものは、 形成層に新しい芽ができる細胞があり、伐採されたり被害に遭うと生命を維持再生するために新しい芽を作りますが、すぐに伸びだす芽(不定芽)と成長が抑制されていて出番を持っている芽(潜伏芽)があるようで、 萌芽として芽生えてくるのは潜伏芽の方が多いようです。
また、老木の根元から新しい枝が沢山出ている樹木があります。これは親木が生活力をなくし先が見えてきたときに根元から新しい枝(ひこばえ)を出し親の後を継ぐ準備をしているのです。
2.萌芽の出やすい木
若い木ほど萌芽力が強く、太く大きくなった木ほど芽生えの力が弱くなります。雑木林の樹木は樹齢20年前後で薪炭材として伐採していたので、萌芽が一番出やすい時期ではないでしょうか。 極端なのは新植した苗木が活着した後で切り萌芽で林を更新しているという例もあるようです。
ところで、ほとんどの広葉樹には萌芽の性質があるので、伐採後は萌芽により親木の後を引き継ぎ林を更新することできますが、スギ、ヒノキ、マツなどの針葉樹には萌芽性がないので、伐採後は新しく苗木を植えないと新しい林を作ることできません。
3.萌芽のためのエネルギー
光合成により栄養分を作り幹や根などあちこちに溜めているのですが、伐採されてしまうと葉がなくなり光合成することできず、幹や根に溜まっている栄養分で新しい芽を出すことになります。 すなわち植物は春から夏にかけては溜まっていた栄養分と新しく作る栄養分で生長しますが、夏から秋にかけて作る栄養分は来春のためのエネルギー源なのです。つまり夏前よりは夏以後の方が体に貯まっているエネルギーが多いので、 萌芽更新を行うためには秋から冬にかけて伐採したほうが萌芽枝の発生がいいということになります。
4.雑木林の生物多様性と働き
昭和30年ごろまでは森林資源を利用し続けていたので雑木林に手が入り常に若々しく樹木が育っていました。でも現在のように森林資源の利用がなくなり雑木林が長い間放置されるような経験はありませんでした。
雑木林の森林資源を利用していた時は、あちこちに樹齢の異なる林があり、その環境に会った動植物が生息できていたので、雑木林は生物の多様性が守られていましたが、今のように森林資源が使われなくなり、雑木林の樹木が高齢化し、 陰樹などが入り込んでくると、林内は暗くなり環境は単純になり生息する動植物も限られたものだけとなり生物の多様性が薄れるだけでなく、森林が持つ効果・働きも薄れてきます。
社会環境が変わり生活様式も大きく変わってしまった現在、昔のような方法で森林資源を使うことできませんが、新しい利用方法を考案し、私たちの生活環境を守ってくれる大切な社会的資本である環境資源(グリーンインフラ)を蘇らせたいですね。