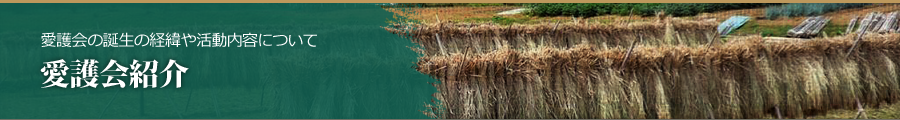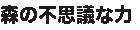ほしいときには降ってくれない雨。でも、一度降り出すと数か月分が一度に降ってくる雨。 雨は恵みになったり、困ったものになったりで、自由にコントロールできないのが雨、昔から水には苦労させられている。でも水に不自由なく暮らせる国が日本です。
ところで、横浜の水は赤道を越しても腐らないと外国航路の船からは非常に喜ばれていたのですが、なぜでしょうか。
1.横浜水道の歴史
明治の初めは人口100名足らずの小さな村だった横浜が、開港により急激に人口が増加し、水不足となった。 そこで井戸を掘り利用したのですが、海を埋め立て横浜を大きくしたため井戸水のほとんどが海水で飲み水にならなかった。 そこで当時の神奈川県知事は英国人技師を招いて相模川の上流に水源を求め明治18年にパイプによる近代水道の建設に着手し、明治20年に完成したので、 昔から上質な水が利用できた。日本で初めての水道でした。
2.神奈川県の水ガメ
神奈川県内には、相模川の上流に相模ダム、城山ダム、宮ケ瀬ダムがあり、酒匂川の上流の三保ダムと合わせ4つのダムがある。これらの水源は富士山のふもとの忍野八海です。 そして県内にすべての水ガメを持っている県は神奈川県だけで、水の心配はほとんどなくなっている。 横浜市の水は相模川水系の水を中心に、遠くは酒匂川の水の恩恵をも受けている。 我々が毎年水源林の保全活動を行っている道志村の水は、相模川水系の宮ケ瀬ダムを経由して横浜に届いている。
3.緑のダム
森林の持つ多面的機能の一つに水源涵養機能がある。降った雨は多孔質の森林土壌に一旦溜められ、徐々に川に流れだす。この機能を“緑のダム”といっている。でも森林土壌の質、状態により現在どの程度の水が含まれていて、 更にどのくらいの水を吸収できるのか、数量的に把握できないのが森林土壌 “緑のダム”の弱みです。
4.森林土壌の質
土壌とは風化した母岩に動植物が分解された腐養物がまざったもので。母岩、生物、気候、地形、時間などの総合作用によって生成されたもので、母岩が風化してできた細かい粒粒だけのものも土と呼ばれることがあるが、 緑の植物が育つ土とは全く異なる。森林土壌は風化した母岩に混入する有機物が毎年大量に供給され、フカフカした多孔質の森林土壌が出来上がっている。でも1cmの森林土壌ができるのに10年ぐらいかかるといわれているので、1mの森林土壌ができるのには千年以上かかっていることになる。 地表植物の有無、針葉、広葉、常緑あるいは落葉など上部の植物により毎年供給される有機物の量に差がある。落ちたばかりの葉は分解される前なので形がはっきりしているが、少し下の層では黒ずみ形がくずれてくる。 それは森の掃除屋と呼ばれる土の中の微生物や小動物が餌として利用し有機物を無機物に分解しているからです。彼らの働きがあるので森林土壌は守られ樹木が育っているのです。でもこの大切な森林土壌も扱いが悪いと一瞬にして失われます。
5.森林土壌の状態
落葉広葉樹の葉は糖分を含み分解者に好まれ、落葉すると素早く分解されるので、落葉広葉樹林(雑木林)の土壌は多孔質で有機物を含んだ厚みのある森林土壌で、かなりの量の雨水を貯めることできる。一方、 常緑針葉樹林(植林地)は林床植物も少なく地表の障害物がないので、地表を雨水が流れやすく、また常緑樹の葉の分解も遅いだけでなく、雨水と共に流れ去っていて供給量も少ないので森林土壌の発達も遅く質も悪い。
ところで乾燥した土壌ならば大量の雨水を吸収することできるも、それでは植物も育たないので、ある程度水分を常に貯めている。土壌中の水分量により受け入れられる水分量が異なるが、一旦飽和状態になってしまうとそれ以上は吸収することができず、 地表を流れたり、土砂崩壊を起こすることになる。手入れされてない植林地の地表は土壌が流されてしまい根がむき出しになっている林が多い。とくにヒノキ林がひどい。
日本の森林地帯は急峻な場所が多く、吸収した大量な雨水でゆるんだ土壌は樹木の根だけでは抑えきれず下方に動き出し、土砂流失や崩壊を起こすことになる。