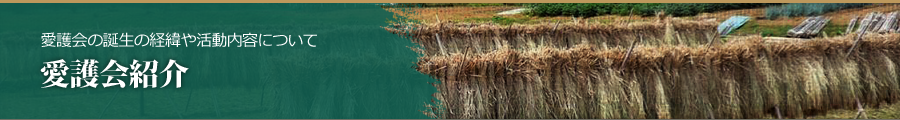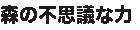地球上の生き物を支え育てるために大気中の二酸化炭素と地中の水分を原料に太陽熱を利用し葉緑素の力で光合成をおこなっているのが緑色植物です。 ところが植物の中にはマヤラン、タシロラン、ギンリョウソウ、ナンバンギセル、ツチアケビ、ヤセウツボ、オニノヤガラなどのように緑色の葉を持たず白っぽい色の植物らしからぬものを見かけます。
1.葉緑素を持たない植物(独り立ちできない植物)
生産者として地球上の消費者を養っているのが葉緑素を持った緑色植物なのですが、植物の中には葉緑素を持たず自分で栄養分を生産せずに他人の世話になっている植物がいるのです。 すなわち、緑色植物の根に寄生したり、有機物を分解している菌に寄生したりしている植物たちです。そして地上に出ている部分は全て繁殖器官の花なのです。
ナンバンギセルはススキやミョウガなどの根に寄生し、ハマウツボはカワラヨモギに、ヤセウツボはシロツメクサやキク科・せり科の植物の根に寄生し、 オニノヤガラやツチアケビはナラタケ菌と共生し寄生主から養分をもらい生活している寄生植物なのです。またマヤラン、タシロラン、ムヨウラン、ギンリョウソウ、ショウキラン、サカネラン、ムヨウラン、 ヒメムヨウランなどは有機物を分解している菌類に寄生して生活している腐生植物なのです。ヤドリギは樹木に寄生して水や養分をもらっていますが葉緑素を持ち光合成できるので半寄生植物なのです。
2.キノコの仲間
菌類の仲間にはキノコがいましたね。キノコの本体は土の中や枯れ木、堆積した落葉の中 に菌糸体を伸ばし生活しています。そしてキノコはその繁殖器官なのです。
キノコに関係している菌類も自立しているものもいれば植物に頼っているものもなど栄養の取り方により腐生菌、寄生菌、菌根菌などに分けられます。
・腐生菌
植物や動物などの遺体の有機物を分解して栄養分を取る菌類で、シイタケ、ナメコ、マイタケなど木材腐朽菌は腐生菌の仲間です。 この仲間はおがくずを原料とした菌床で栽培できるので工場で短期間に大量栽培できます。
・寄生菌
生きた動植物や他の菌類に寄生して宿主から栄養分をもらっている菌でナラタケ、ヒラタケなどです。 セミ、トンボ、クモ、蛾の幼虫等生きた昆虫に寄生してできる冬虫夏草もこの仲間です。
・菌根菌
植物の根に菌根を形成する菌類です。菌根菌の菌糸は植物の根の表面を覆い、病原菌の侵入、乾燥、養分の欠乏などから植物を守るとともに土の中から吸収した水分、 窒素、リン酸、カリ等ミネラルを植物に与えているのです。一方植物は菌根菌に栄養分を与えており共生関係にあります。
マツタケが代表的なキノコです。試験的栽培は成功しているようですが、難しすぎコストが掛かりすぎ、いまだに天然ものに頼らざるを得ない状態です。
以上のように腐生菌は枯れ木や落ち葉を分解する森の掃除屋さん。寄生菌は老木、弱った樹木を間引く役割。菌根菌は樹木の生長を助ける役割をしているのです。
3.植物と菌類との共生
ドングリの実は丸く大きいので斜面を転がって生活範囲を広げているといわれている。でもこれでは斜面の下の方ばかりに広がって、斜面の上にはいけないのですが、 ドングリは栄養の詰まった大きな実なので、動物たちの大切な餌となっている。特に一度に食べず土の中に保存する性質のあるリス、ノネズミ、カケスなどは、 斜面の上部にも運び埋め蓄え、食べ忘れた種子が生えてくることで斜面の上部にも生活範囲を広げている。