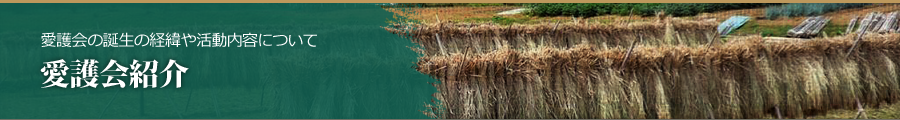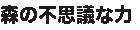地球上の全ての生命を支えている植物達は、花を咲かせ実らせた種子で子孫を繋ぐことを原則としている。そこで長い年月の間に、花の形や付属物、受粉の仕方、種子の散布方法などに素晴らしい進化が見られる。いったん芽生えてしまうと動けないのが植物ですが、種子は自由に動くことのできる姿です。そこで種子にはどんな工夫が施されているか見てみましょう。
1.種子の役割
種子には生命の機密情報がいっぱい詰まり、着地した場所で新しい生活が始められるように栄養たつぷりの弁当を持っているのが普通の種子です。堅い殻で守られた種子は親が耐えられないような乾燥や寒さをしのぎ生命を繋ぐ。また親から引き継いだ遺伝子情報は種子ごとに少しづつ異なり環境の変化に適応しながら今まで生命を繋いできたのです。
2.種子の旅の仕方
1)風散布 (風に任せ風に乗る)
一番簡単な旅の仕方です。小さく軽い沢山の種子を作り風に任せてしまう。でもそれだけではありません。風に乗りやすぐするために下記のような工夫がなされている。
*綿毛のパラシュート *翼を広げた飛行隊 *埃のように微細な種
2)人や動物の利用 (ヒッチハイク)
風任せの散布は沢山の種子を作るのに多くのエネルギーを使う割には効率が悪い。もう少し効率よく種子の散布をするために、人や動物を利用することにした。そのために利用する相手に応じて種子に様々な工夫が凝らされている。特に鳥を対象にした種子には発芽抑制物質を含んだものが多く、鳥の胃袋で発芽阻害物質を擦り落とした後、遠くへ運ばれることを望んでいる。
*付着散布(ヒッツキムシ) *鳥、動物の被食散布 *動物たちの貯食散布
*アリさんの利用(エライオソーム)
3)水の利用
水辺の植物は川の流れに種子をまかせるような構造を作り出した。また雨の水滴のカではじき出したり、雨水で種子が湿り粘りけが出てきたときに動物の足・靴・タイヤなどにくっつき運ばれる工夫をした種子もでてきた。
4)自力ではぜ飛びだす
風や動物に触られた時に自分で表をよじりはじかせ種子を飛ばす方法ですが、足元近くにしか落下せず遠くまで飛ばすことできません。そこで、アリさんも利用。
5)アリの利用
自力で種を飛ばしても思ったほど遠くへ飛ばせないので、アリの好きな物質エライオソームを種子に付け、さらにアリの巣まで運ばせ、エライオソームを食べ終わったらその近くに種子を放置してもらっているのです。
3.種子の旅行時間(体眠、埋土種子)
運ばれた場所の環境が悪いときは、発芽しても生長できないのでその場所で地中に潜り休眠する術を身に付けた。このような種子を埋土種子といい、地上の環境が好転するまで気長に待つことができるのです。先駆植物には埋土種子が多く、気長に数十年も待ち続けて居るものもいる。大賀ハスは千年以上眠っていた。
以上のように種子には複雑な仕掛けがあります。紙面のスペースがなく個々の植物名を入れることできませんでした。面倒でしょうがご自分で入れてください。