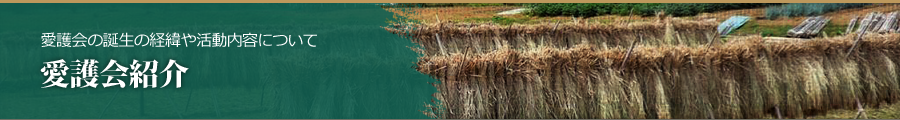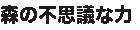やっと秋の気配を感じられるようになりました。十五夜のお月見のお供えはどうされますか。お団子にススキ。ススキは稲穂に見立てて豊作を祈るために飾られます。 立待月、居待月、臥待月、久しぶりに聞く名前ですね。しばらく無心で月でも眺めませんか。ところで、ススキ、オギ、ヨシ、三者ともイネ科の植物で非常によく似ています。どのように区別していますか。
1.ススキ
ススキは尾花という名前で秋の七草に入っていて、昔からお月見にはなくてはならないものですね。日当たりの良い乾いた場所に株状にまとまって生えるので非常に分かりやすいですが、この頃は見つけにくくなっています。 どうしてでしょう。水辺のオギと同じように細い葉の真ん中に白い筋が通っています。穂は20-30㎝ぐらいの総(ふさ)が十数本集まっていて、その総には金色の毛でおおわれた小さな粒粒(小穂)が並んでいて、一面の金世界になります。 小穂の中には芒(ノギ)という長い毛が一本あるのが特徴です。芯がしっかりしているので茅葺き屋根の材料に使われ、炭俵や冬囲いなどにも使われました。ススキにノギあり。
2.オギ
ススキとは異なり、アシと同じように湿地に生え、伸びた根からタケノコのように一本ずつばらばらに芽を出し一面に広がるので、退治しようとしてもちぎれた根から新しい芽が出るので退治しきれません。 葉は細くススキと同じように真ん中に白い筋が通ります。小穂には芒はなく銀白色の細長い毛が生えふさふさとしておりオギが一面に広がると素晴らしい銀世界です。芯があるのでススキと同じように使われますが、むしろやスダレなどにも使われます。
3.アシ・ヨシ
昔はアシといはれていましたが、アシは「悪し」に通じるということで、“ヨシ”と呼ばれるようになりました。オギと同じで水辺が好きで、しかも根から一本づつばらばらに芽を出し一面に広がります。穂は淡紫色でやや大型です。 葉はススキやオギよりは広く、白い筋はありません。大きな違いは芯が中空になっていて軽いので、スダレに利用されています。
4.秋の七草
「秋の野に 咲きたる花を指折り かき数ふれば 七種の花」
「萩が花 尾花葛花撫子の花 女郎花また藤袴 朝貌の花」 山之上憶良
(尾花(オバナ)はススキ、朝貌(アサガオ)はキキョウです)
春の七草は七草がゆに象徴されるように食用となる植物ですが、秋の七草は美しい花が対象となっています。でも野原でみられる花はいくつあるでしょうか。私が子供のころは全ての花が身近で普通にみられました。今ではハギ、ススキ、クズ程度になってしまい、 残りの花は家の庭で栽培されているものがほとんどです。秋の七種の名前はおぼえにくいので、「ハスキーなお袋」とか「お好きな服は」とか覚え方があるようですが、覚え方も忘れてしまいそうですね。
5.ススキに寄生する植物
ススキの根に寄生するのがナンバンキセルです。葉緑素をもたず自分では光合成せずススキから直接栄養をもらっている 寄生植物 です。初秋に繁殖器官、花だけを地上に出し、種子を作ります。寄生植物には有名な大きな花を咲かせるラフレシアがそうです。身近にみられるのはヤセウツボですね。タシロラン、ツチアケビ、ヤツシロラン、ギンリョウソウ、 マヤラン、オニノヤガラなどは葉緑素を持たず菌が分解した栄養分に依存している 腐生植物 です。