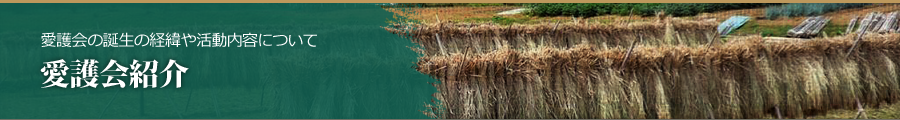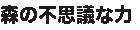雑木林は生活に必要な燃料を得るために、直径10-15㎝程度の樹木を数年おきに一定面積を皆伐、更新しながら長年利用してきました。ところが、 昭和30年代になり石油が普及し始め雑木林の木材資源を使わなくなり60年以上もたち、雑木林は更新されることなく年を取ってきました。雑木林は人家の近くにあるので常に人手が入り日常利用されていた林なので、 人の手によって維持、管理され遷移の止まっていた林です。利用していた時の更新方法は苗木更新、萌芽更新、天然下種更新の三つの方法がありました。
1.苗木更新
苗木を新しく植え更新する方法です。植え方は根が隠れる大きさの穴を掘り苗を入れ土をかけ、しっかり土と根が密着するように踏み固めること。土が足りないときは山側の土で補給。
新治市民の森では学校林、10周年記念植林地、20周年記念植林地、向山植林地と四か所の更新地がありますが、全てこの方法で行っています。
2.萌芽更新
広葉樹は全て切り株から新しい芽(萌芽)を出す性質を持っています。とくにコナラ、クヌギなどの若木は萌芽力が強いので、20年生前後の若木を伐採し燃料として利用していた時代の雑木林では萌芽による更新が行われていました。
切り株からは沢山の萌芽が出てくるので、2,3年後には勢いよく伸びている2,3本の幹を残し生長の悪い萌芽枝を除く“もやかき”が必要です。
学校林、10周年記念植林地で間伐した切り株から萌芽が出てきていますので、上手に育て更新しましょう。
3.天然下種更新
天然の力を利用する更新方法です。更新したい場所の中や周りに、種の出来る親木を1,2本残し、落ちた種をその場で発芽させ育てる更新方法です。種の落ち方や発芽率にむらがあるので、更新したい場所に適当な間隔をあけて上手に木を育てことできません。
10周年記念植林地では横の作業道に残したコナラの親木からの種で、20周年記念植林では伐採した樹木の中にコナラの親木があったので、そこから落ちたドングリが発芽して植林木とともに成長しています。
4.向山栗林の更新
A地区は新治小学校4年生、B地区は三保小学校5年生の力を借りて苗木による更新が終わりました。残っているA地区とB地区との間の場所ですが、苗木を植える方法と天然下種更新の方法で更新をしたいと思います。
*苗木を植えての更新: 比較的傾斜のゆるい場所では苗木による更新。
*天然下種更新: 急傾斜地で足場の悪い場所では種を蒔く。
この場所には親木となる木がありませんので、私たちが親木となり種を蒔きます。一か所に移植ごてで4,5cmの深さの穴を3,4個堀り、そこに一粒ずつ種を植えしっかり踏みつけてください。 発芽した芽が素直に伸びられるように種を蒔いた場所の上は草など障害物を取り除ききれいにしておいてください。発芽率が悪いので一か所に数個まとめて蒔きます。