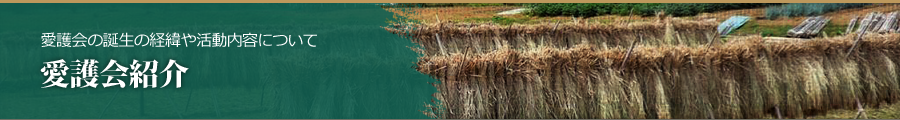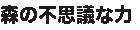昨今のように季節に合わない極端に暑い日が続くと植物たちの生長が良すぎ、花の咲く時期もどんどん前倒しとなり秋に咲く花がなくなるのではと心配しませんでしたか。 種子植物が花を咲かせ子孫を残してきた長い年月の間には気候変動の激しかった年もあったでしょうが、花の咲く時期が少々ずれても、春の花は春に、秋の花は秋に咲き今日まで子孫をつないできました。 それではどんな仕掛けで植物たちは花を咲かせる時期を感じ取っていたのでしょう。
1.花咲く時期を知る
一旦芽生えてしまうと動くことのできないのが植物ですが、春の訪れとともに新しい葉を出します。生まれたばかりの葉は弱々しく紫外線に弱いので様々な色素で保護されています。 日を追って一人前の緑色の濃い葉となり光合成を励みますが、暑いからと言って避暑に行けず、冬寒いからといって暖かい地方へ移動することできないので、暑さにも負けず、寒さにも負けない種子で環境の悪い時期を過ごすことにしました。 ということは環境が悪くなる前に種子を作る必要があります。花を咲かせ種子を作るには時間がかかるので、環境の変化を早く感じ取り蕾を作る指令を出す物質を作るのも葉の大きな仕事の一つなのです。
2.葉の仕事
葉の仕事というと、すぐに光合成を思い浮かべますが、それだけではなく葉は沢山の仕事をしています。光合成では体を作る栄養分を作りますが、食害や環境の変化から体を守る物質、 生長を左右する物質、樹体内や近くにいる仲間への伝達物質などいろいろな物質も葉で作っています。外界の変化を感じとり花を咲かせる時期を知り指示を出す物質づくりもその一つです。
キクの“電照栽培”聞いたことありますね。人工的に昼の長さを調節し花を咲かせる時期を決める栽培方法です。春咲く植物は昼の時間が長くなるのを感じ、逆に秋咲く植物は昼の時間が短くなるのを感じて蕾を作る指令を出しているのです。 日の出日の入りの時刻は気温に左右されることなく夏至を過ぎれば昼の時間は短くなり、冬至を過ぎると日ごとに昼の時間は長くなっていきます。この現象を感じ取り芽に蕾を作る指令を出すのが葉の役目です。 昼の長さが幾らになったら葉からその指令がでるかは植物によって異なります。季節を先取りするような気温の変化があっても植物たちはそれに惑わされることなく一年の仕事をしているのです。
3.植物の体をめぐる伝達物質
植物の細胞の周りには固い細胞壁があり、病原菌の侵入を防いでいます。防ぎきれず病原菌に侵されると、侵された細胞はすぐに死んで病原菌を細胞内に閉じ込めます。そして、死ぬ前に病原菌が侵入したことを他の葉に知らせるために伝達物質を作り健全な葉に伝達し、 伝達を受けた葉は抗菌物質を作り始めます。この伝達物質は容易に揮発性物質に形を変えることできるので気体となり近くの植物にも伝わり抗菌物質を作り始めます。花粉を運んでもらうために昆虫を呼び寄せる花の香りとは異なり、植物同士のコミュニケイションのための物質です。 園芸品種で斑入りの葉が好まれますが、これは菌に侵され葉緑素のなくなった葉の姿です。
4.休眠打破
冬を越し春咲く植物は夜の時間とは別に年内に咲かないように開花防止の指令が出ています。そのために、40C以下の低温に一定期間さらされ、開花防止のカギを外し、その後の積算温度によって開花できるのです。 この低温処理による冬芽の覚醒を休眠打破と言います。